日々の暮らしの中では、長期的な視点から計画を立てたり、自分を振り返ったりすることは難しいかもしれません。スピードが早い現代に生きる私達は、毎日やるべき課題に追われているため、無理もないことです。
思いがけない休みの日ができた時に、ふと長期計画を立てたり、自分を振り返ろうとしたりしても、いったい何から始めていいか分からなくなった経験があるかもしれません。
また日常生活に染まってしまっている私達の視野では、何かを考えようとしても、今目の前にある課題に対してとりあえずの解決策を思いつくだけで、将来私達が何をしていきたいかや私達がどんな人になりたいかなどを考えるのは難しいでしょう。
一方で、Kevin Ngoはこうした状況に鋭い洞察をしています。「望む人生を創るために時間を作らなければ、結局は望まない人生に対処するために多くの時間を費やすことを余儀なくされる」と。
そこで、長期的な計画を立てたり、自分を振り返ったりするための科学的に優れた方法はあるのでしょうか。
一つの答えは、いつもの自分の生活空間から物理的に離れた場所(例えば地上から3万3000フィート離れた飛行機の中や、海外もしくは国内旅行先など)に移動して考えることでしょう。
社会心理学者のYaacov TropeやNira Libermanらが提唱している解釈レベル理論 (Construal Level Theory) では、対象との心理的距離と解釈レベルに相関関係があることを示しています。
解釈レベル理論では、対象や出来事からの時間的・空間的・社会的距離は相互に関連すると唱えています。これは自分の苦手な人に対して(社会的な距離が遠い)、離れた場所に座ったり(空間的に遠い)、丁寧な表現になったり(英語の場合、時制が過去形となり、時間的に遠い)することからもわかると思います。
また、解釈レベル理論は、私達が対象や出来事から時間的・空間的・社会的に離れると、その対象や出来事に対する私達の思考の抽象化の程度もあがると唱えています。たとえば被験者の時間的距離や社会的距離を離れさせることで、細部に注意を向けると成績が下がり、かつ大局的な見方が必要とされるゲシュタルト完成課題のパフォーマンスが向上したことが示されています。
今回の私達の例に戻ると、あえて日常の自分のいる場所から空間的距離をおくことは、時間的距離の離れた自分の将来への考察や、普段の自分の行動を振り返るといった大局的な考察をする際に、非常に有利にしてくれるのです。 イギリスの作家のDavid Mitchellもこのことを端的に示しています。「遠くまで旅をすれば、君は自分自身と出会う」と。
心理学的研究に頼らずに、私達にも馴染みのある昔からの格言を用いるとすると、「木を見て、森を見ず」という状態になるのを防ぐために、一度自分の周囲の木から遠く離れた場所に行き、その場所から自分を見直すことで、新たな発見が得られるということでしょう。
私自身ここ数年は、年間で飛行機に50時間以上乗っていますが、飛行機の窓から雲ひとつない空の一面の青色を見ながら、今後数年から数十年単位のスケジュールを考えたり、自分の行動を振り返ったりしています。それによって、普段の自分では気づかない事柄に気づいたり、新しい抽象的なアイデアが生まれたりするなど、空間的距離の遠さが自分の人生に与えるインパクトを体感しています。
あなたも異なる視座からの長期プランニングや振り返りに、シンプルな「距離的移動」という手段を使ってはいかがでしょうか。
参考文献:
Trope, Y., & Liberman, N. (2010). Construal-level theory of psychological distance. Psychological review, 117(2), 440.

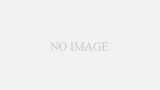
コメント