日本人ならばほとんど皆が知っていると思われる夏目漱石。彼も自分の道、彼の言うところの「自分の本領」、を見つけるまでは人知れず心の中で苦悶していました。
『その日その日はまあ無事に済んでいましたが、腹の中は常に空虚でした。空虚ならいっそ思い切りがよかったかも知れませんが、何だか不愉快な煮え切らない漠然たるものが、至る所に潜んでいるようで堪まらないのです。』
この内なる感覚は、自分も含めて、現代の多くの人が持っている感覚と似ているかもしれません。彼はその「空虚さ」を振り払うために、今後自分が「どちらの方角」に進んだらよいのか模索します。
『私は始終中腰で 隙があったら、自分の本領へ飛び移ろう飛び移ろうとのみ思っていたのですが、さてその本領というのがあるようで、無いようで、どこを向いても、思い切ってやっと飛び移れないのです。私はこの世に生れた以上何かしなければならん、といって何をして好いか少しも見当がつかない。私はちょうど霧の中に閉じ込められた孤独の人間のように立ち竦んでしまったのです。そうしてどこからか一筋の日光が射して来ないかしらんという希望よりも、こちらから探照灯を用いてたった一条で好いから先まで明らかに見たいという気がしました。ところが不幸にしてどちらの方角を眺めてもぼんやりしているのです。ぼうっとしているのです。あたかも囊の中に詰められて出る事のできない人のような気持がするのです。私は私の手にただ一本の錐さえあればどこか一カ所突き破って見せるのだがと、焦燥り抜いたのですが、あいにくその錐は人から与えられる事もなく、また自分で発見する訳にも行かず、ただ腹の底ではこの先自分はどうなるだろうと思って、人知れず陰欝な日を送ったのであります。』
ただ私が思うに、夏目漱石の偉大なところは、その空虚さや陰鬱さといった感覚を、自分に正直に、長期間持ち続けたことにあると思います。彼は「皆そういうものだ」などと自己説得せずに、その感覚に向き合い続けたのです。
その結果、彼は、英文学を専攻する当時の日本の学者が英文学の本場の批評家に物怖じして迎合する態度は違うと考えました。彼は英文学の本場の批評家の考え方と自分考え方の矛盾をしっかりと認識して説明することで、『日本の文壇には一道の光明を投げ与える』ことを目指したのです。
他者や通説に安易に迎合せずに自分の考え方を大切にする姿勢を彼は『自己本位』と呼び、それが現在にまで伝わる彼の作品に繋がっているのです。
夏目漱石は、過去の彼のような煩悶を持つ人々へメッセージを送っています。
『私の経験したような煩悶があなたがたの場合にもしばしば起るに違いないと私は鑑定しているのですが、どうでしょうか。もしそうだとすると、何かに打ち当るまで行くという事は、学問をする人、教育を受ける人が、生涯の仕事としても、あるいは十年二十年の仕事としても、必要じゃないでしょうか。ああここにおれの進むべき道があった! ようやく掘り当てた! こういう感投詞を心の底から 叫び出される時、あなたがたは始めて心を安んずる事ができるのでしょう。容易に打ち壊されない自信が、その叫び声とともにむくむく首を擡げて来るのではありませんか。すでにその域に達している方も多数のうちにはあるかも知れませんが、もし途中で霧か靄のために懊悩していられる方があるならば、どんな犠牲を払っても、ああここだという掘当てるところまで行ったらよろしかろうと思うのです。必ずしも国家のためばかりだからというのではありません。またあなた方のご家族のために申し上げる次第でもありません。あなたがた自身の幸福のために、それが絶対に必要じゃないかと思うから申上げるのです。もし私の通ったような道を通り過ぎた後なら致し方もないが、もしどこかにこだわりがあるなら、それを 踏潰すまで進まなければ駄目ですよ。――もっとも進んだってどう進んで好いか解らないのだから、何かにぶつかる所まで行くよりほかに仕方がないのです。』
『この私は学校を出て三十以上まで通り越せなかったのです。その苦痛は無論鈍痛ではありましたが、年々歳々感ずる痛みには相違なかったのであります。だからもし私のような病気に罹った人が、もしこの中にあるならば、どうぞ 勇猛 にお進みにならん事を希望してやまないのです。もしそこまで行ければ、ここにおれの尻を落ちつける場所があったのだという事実をご発見になって、生涯の安心と自信を握る事ができるようになると思うから申し上げるのです。』
彼の個人的成功体験は、現代の人々の成功体験と同じで、生存バイアスの強くかかった事象です。一方でそのことを考慮に入れたとしても、彼の辿ったストーリーとその彼が作り出した文学は現代の私達にもいまだ響いています。
参考文献:『私の個人主義』 夏目漱石
(文章では敬称を省略しております。)

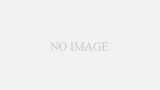
コメント